ノイバラの花も、もう終わり・・。散歩道には、白い花びらがはらはらと散っているのを見かけるようになりました。ノイバラの花を見ると、いつもわたしは、あの大好きな蕪村の俳句
「愁(うれ)ひつゝ岡にのぼれば花いばら」
を、思い出します。蕪村のこのような心情には、やはり清楚なノイバラの花がよく似合うように思うからです・・。
穂刈瑞穂さんが書かれた「モンテーニュ よく生き、よく死ぬために」を、もう1か月近くもランダムにゆっくりと読んでいます。
穂刈瑞穂さんの本は、「プルースト読書の喜び 私の好きな名場面」筑摩書房と、プルーストの評論の文学と芸術を穂刈さんが選んで本になさったもの2冊、(「プルースト評論選Ⅰ文学篇」ちくま文庫「プルースト評論選Ⅱ芸術篇」ちくま文庫)を、読んでいたので、今回で4冊目になります。
特に「プルースト読書の喜び」は、「失われた時を求めて」の中から穂刈さんのお好きな名場面を語るというもので、お人柄がしのばれるような静謐な語り口で、とても好感を持って読んだ読んだのを思いだします。
この本も、モンテーニュの「エセー」から穂刈さんのお好きな文をとりあげて、ご自分のご感想と共に語られているのですが、ゆっくりと味わいながら読まれたことがよくわかりました。
「モンテーニュ」は、わたしにとって未知の人でしたが、「私は何を知っているか Que sais-je(ク・セ・ジュ) 」を、自分の座右の銘にしていたこと、
そしてそれをソクラテスから学んだことを知り、彼の人生哲学の深さは、幼いころから古典の素養を学ぶなど英才教育を受けたことだけではなく、人間としての魅力にもあふれていた人だったからなのではと、想像をめぐらせてしまったのでした。
「自分の無知を知ることが知恵の真の起源である」という彼の哲学は、すんなりとわたしのこころにも入りました・・。
ところで、著者の穂刈さんは若いころに、2度もフランス政府の招待でパリに遊学なさっており、フランス政府にはとても感謝なさっているとのこと。そして当時のパリでの生活はとても楽しく、パリやフランスをこよなく愛するようになり、その後の人生を、フランス文学を日本に伝える道に進まれるようになったのだとか・・。
そういえば、「プルースト 読書の喜び」のあとがきには、2008年に長かった大学の勤めが終わったあと、思い切って日本を離れて大好きなパリに移り住まれたと書かれていたのを思い出したのですが、その後2021年7月10日に「念願のパリ」で83歳で亡くなられたのを最近知りました。
穂刈さんの命日の7月10日は、プルーストの誕生日ですので、プルースト研究者でもあった彼のプルーストとの不思議なご縁も感じ、「モンテーニュ」の本のサブタイトル、「よく生き、よく死ぬために」という言葉は、穂刈さんご自身の人生哲学でもあったのでは・・と思いをはせた読書でした。














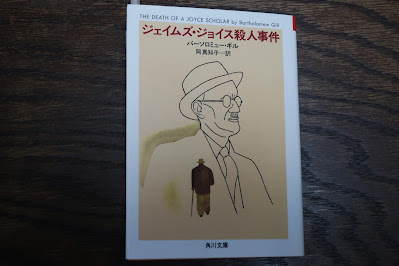








.JPG)





