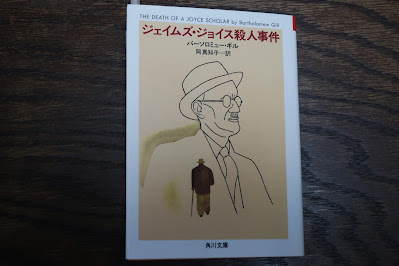毎年この季節に見かけるノササゲの実です。
濃紺の色がシックですが、
ほかの実は、もう干しブドウのようになってしまいました・・。
この本には、マルセル・プルーストが、16歳の頃から、母との永遠の別れの時の34歳まで、二人の間で交わした手紙149通が載っています。
最初の手紙の冒頭には「ぼくのすてきなお母さま」二通目は、「ぼくの大好きなお母さまへ」
そして、母からプルーストへは、「可哀そうな狼さん」「坊や」「わたしのかわいい坊や」などから、「わが子へ」と次第にかわっています。
これらのお互いへの呼びかけの言葉からも、ふたりのあいだでの愛情の深さは感じられるのですが、深いからこそプルーストが、精神的、経済的にも自立できていなかったことや、ぜんそくなどの虚弱体質のことなどに関する母の心配は、とても大きかったのではと思います。
そして、プルーストは、母の亡きあとにこのことに気づき、自分がどれだけ母に心配をかけていたかを、痛切に反省し涙したのではと想像しました。事実、プルーストはしばらくの間は立ち直れなかったほどだったということでした。
母は愛情深く、教養もある女性で、プルーストにとっては、まさに何でも話せる「ぼくのすてきで、大好きなお母さま」だったことは、この書簡集から読み取れました。
ところで、プルーストの「失われた時を求めて」の4人の翻訳者の方々はそれぞれ、本の中での母親や祖母の呼び方を、
井上究一郎さんは、「ママ」 「お祖母さま」
鈴木道彦さんは、「ママン」 「お祖母(ばあ)ちゃま」
吉川一義さんは「お母さん」 「おばあちゃま」
高遠弘美さんは「お母さん」 「お祖母さま」
と訳していらっしゃいますので、それぞれ引用してみます。
(主人公がまだ子供だったころ、大好きな母親が来客のためにお休みのキスをしに来れなくなったことで、がっかりして感情が高ぶっていたところ、父の特別な口添えもあり、母親が自分のベットに来てくれることになった場面です。)
引用
・-・-・-・-・-・
井上究一郎さんの訳
「あら、私の小さなおたからさん、私のかわいいカナリヤさん、もうすこしでこのママもいっしょにおばかさんになるところね。さあさあ、あなたもねむくはないし、ママもねむくはないのだから、いらいらしていないで、何かしましょう、あなたのご本を一冊とりましょうね。」
「失われた時を求めて」Ⅰ第一篇 スワン家のほうへ ちくま文庫 65p
・-・-・
鈴木道彦さんの訳
「まあまあ、この可愛いおいたさんたら、もうちょっとで、ママンまで、お前と同(おんな)じおばかさんになるとこね。さあ、お前もママンも眠くないんだから、いらいらするのはやめて、なんかしましょうよ。なにかご本を読んだらどうお?」
「失われた時を求めて」Ⅰ第一篇スワン家のほうへ 集英社文庫 97p
・-・-・
吉川一義さんの訳
「あらあら、こんなことをしていると、かわいいお馬鹿さんになっちゃいそう。さあ、あなたは眠くないんだし、お母さんも眠くないんだから、いらいらしないで、なにかしましょう。ご本でも読みましょう。」
「失われた時を求めて」1 スワン家のほうへⅠ 96p
・-・-・
高遠弘美さんの訳
「わたしのかわいい金貨(ジョネ)さん、ちょっぴりおばかなカナリヤ(スラン)さん、こんなふうだとお母さんまであなたみたいにばかになっちゃうわ。ねえ、お母さんもそうだけど、あなたも眠くないんだったら、気を落ち着けなきゃだめね。何かしましょう。あなたの本を読む?」
「失われた時を求めて」①第一篇「スワン家のほうへⅠ」 103p
・-・-・
翻訳者の方々はそれぞれのお考えで、熟考なさった結果だと思うのですが、わたしは鈴木道彦さんの「ママン」という翻訳が、好きです。
プルーストの場合、父は高名な医師、母は裕福で教養のある女性ということで、恵まれていたブルジョア階級という家庭環境でしたので、世紀末という時代背景も入れて考慮しますと、わたしは手紙でも権寧さんが訳されているように、母親のことは尊敬と親しみを込めて「お母さま」と呼ぶのも自然かなと思ったのですが・・。
失礼させていただき、井上究一郎さんの翻訳の「ママ」を、「お母さま」に置き換えてみますと、こんな感じになりました。
・-・-・
「あら、私の小さなおたからさん、私のかわいいカナリヤさん、もうすこしでお母さまもいっしょにおばかさんになるところね。さあさあ、あなたもねむくはないし、お母さまもねむくはないのだから、いらいらしていないで、何かしましょう、あなたのご本を一冊とりましょうね。」
フランス語では、母は「mère」と「maman」のふたつですが、それにしても日本語での母の呼び方は、多様性にあふれていて驚きます。
この本「プルースト・母との書簡」の場合、権寧さんが訳された「お母さま」は、ぴったりで、手紙から感じられるプルーストの母への愛情と尊敬が、より深く感じられたのでした。