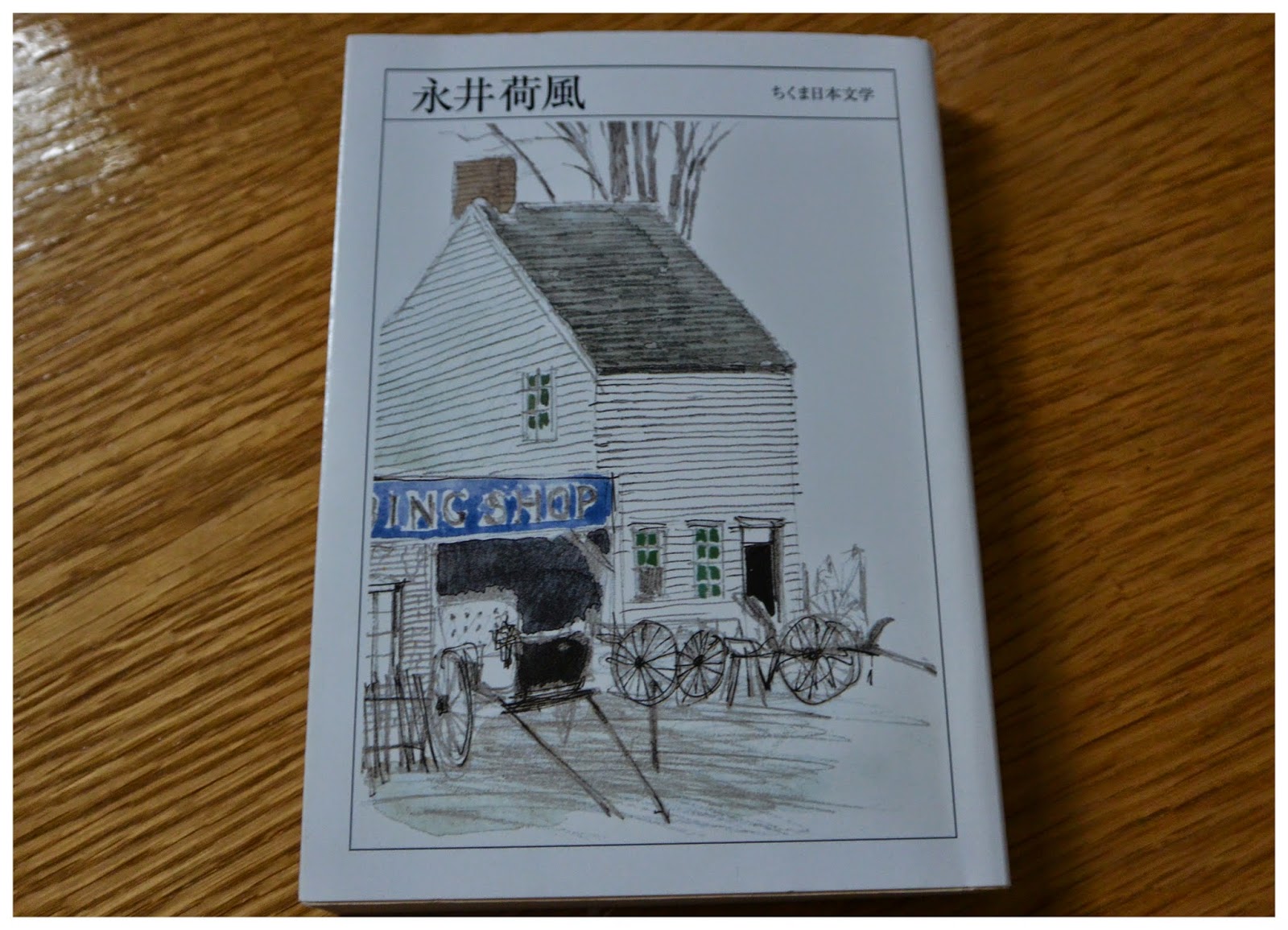たしか、白檀の扇子があったはずと、箪笥の引き出しをさがしてみましたら、
古布のバッグといっしょに、ひっそりと片隅にありました。
白檀の扇子のことを、檀香扇(たんしゃんせん)というそうですが、扇をあおいでみますと
白檀のすばらしい香りが、ただよってきます。
扇の出てくる短歌と俳句にこんなものがあります。
「かたみとぞ風なつかしむ子扇の要あやふくなりにけるかな」
与謝野晶子
「畳む時扇淋しき要かな」
久保田万太郎
短歌も俳句も、どちらも「要」が大事のようです。
こだわりのあった叔父の審美眼には敬服してしまうのですが、わたしの大事な宝物です。
白檀の扇子のことを、檀香扇(たんしゃんせん)というそうですが、扇をあおいでみますと
白檀のすばらしい香りが、ただよってきます。
扇の出てくる短歌と俳句にこんなものがあります。
「かたみとぞ風なつかしむ子扇の要あやふくなりにけるかな」
与謝野晶子
「畳む時扇淋しき要かな」
久保田万太郎
短歌も俳句も、どちらも「要」が大事のようです。
古布のバッグの方は、叔父の贈り物でしたが形見になってしまいました。
この物入れを見ると、源氏物語の絵巻物に出てくるような女性の着物姿を
思い浮かべてしまいます。
この物入れを見ると、源氏物語の絵巻物に出てくるような女性の着物姿を
思い浮かべてしまいます。